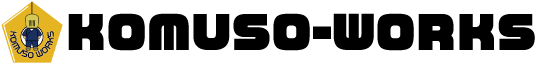政府が「働き方改革」を打ち出して以降、大企業に限らず中小企業でも作業の効率化は経営課題の一つとして認知が上り、さらには2019年4月1日より施行された「働き方改革関連法案」により効率化への動きは企業の優先事項となりつつあります。
各種メディアがデジタル化・効率化を特集し、今年に入ってからはさらにコロナの影響でオンラインでの作業や在宅勤務による仕事の進め方に関心が高まっています。
わたし個人的には、この流れは更に加速し在宅ワークやフリーランスと言った形で働く人は今後ますます増えていくと考えています。
在宅やフリーランスと言った働き方が増えていく中で、経営者として自分(人)がやるべきことと人以外に任せることを取捨選択し効率よく業務を遂行しなければならない。
そんなことを思案する中でわたしは改めてRPAに注目してみました。
RPAとは?

RPAとはロボティック・プロセス・オートメーション(Robotic Process Automation)の略で、コンピューター上で定型的な作業をソフトウェア(ロボットもしくはボット)を利用し自動的に行う(オートメーション化する)ことで、仮想的労働者と呼ばれることもあります。
では、いったい何ができるのか?
正直、一言では言い表せないほどRPAのできることは多岐にわたります。
たとえば…
・帳簿の入力や伝票の作成など経理的な業務
・顧客データの管理や営業支援システム(SFA)へのデータ入力など営業事務的な業務
・社員情報や出退勤などの労務管理といった人事的な業務
・WEBサイトのログ解析データや成約(購買や資料請求)の情報を取り纏めたレポート業務
このRPA、意外と歴史は古く1980年代には既にベースとなる自動化ツールは登場しており、セキュリティーの問題などで一時下火になっていまっしたが、2010年代になり次世代ツールとして開発が進み導入事例が増えてきました。国内においては2017年にガートナー ジャパン株式会社が行った調査では14.1%の企業が導入済み、6.3%が導入中という5社に1社が利用しているという結果がでており、株式会社MM総研の2020年1月にリリースされた「RPA国内利用動向調査2020」によるとRPAの導入率は38%となっており、わずか3年足らずで約2倍に増えているとの結果が出ています。
RPAはハードルが高い?
さて、ここまで急速に伸びているRPAだが問題がないわけではない。
先に述べた2017年のガートナージャパン株式会社の調査には”導入中”という部分が物語るように、以前はRPAを利用するまでにはいくつかのハードルがありました。
・現状行っている業務の分析
・RPAに置き換える業務の洗い出し
・上記を明確にしたうえでのシステム設計、そして開発…
このようにRPAを使えるようにするまでに多額の費用と時間を必要としました。
更に導入後に関しても保守や拡張運用にも高度な知識と費用が求められ、場合によってはRPA専門のオペレーターを雇うという本末転倒な事態にもなり得ました。
これらの理由から以前は大企業や中堅企業を中心にしか導入されていなかったRPAが、この3年でどうして利用者が急増していったのでしょうか。
ノウハウの蓄積とプラットフォーム化
子のエントリーのテーマ、わたしが改めてRPAに注目してみた理由。
それはあるサービスを知ったことが切っ掛けです。
そのサービスを最初に知ったのは前々職時代のある知人からでした。
以前人材募集をお願いしていたディップ株式会社(以降ディップ)という会社が今年の9月にRPAプラットフォームをサービスインしたらしい。
プラットフォーム化のメリットは何と言っても利用するまでの期間が短い事と価格にある。これにより今までRPA導入にあった高いハードルはある程度取り除かれたと思う。
わたしの中ではディップと言えばバイトルやはたらこねっとなど人材募集のイメージが強かったのだが、AIなどのテクノロジーには2016年から進出していたらしく、2019年9月にリリースした「コボット」シリーズでは、人材派遣向けの「HRコボット」・賃貸管理会社向けの「不動産コボット」・面接日程を管理する人事向けの「面接コボット」など、業種や業務に特化したRPAを提供してきた。
業種・業務に特化するとどの様なことが起こるかの?
わたしも前職・前々職で嫌というほどやってきたのですが、ノウハウの蓄積がしやすく営業展開もしやすい、結果提供価格も抑えられるというメリットがあります。
ディップの「コボット」シリーズの場合、わずか1年足らずで5000社の運用実績(2020年7月末時点)を積み上げ、そこで出た様々な課題や問題点を基に今回「コボットPlatform」という新サービスを立ち上げたということです。
コボットPlatformの特徴
コボットPlatformの最大の特徴はUI(ユーザーインターフェース)。
数多くあるアクティビティと呼ばれる機能(やれること)を組み合わせてロボットを作成することができるので、プログラミングやRPAの知識がなくてもわかりやすい。
ファイナルファンタジーでアビリティーを組み合わせて好みのキャラを作ったり、ミニ四駆でモーターやタイヤを変えたり重り数や位置を変える感覚だろうか。
また、「もっと専門的なことをやらせたい」とか「もっと煩雑な作業をさせたい」などのニーズにも応えられるように拡張性があるような作りになっている。
ちなみに「コボットPlatform」は大きく3つの機能で構成されており、ロボット開発を行うための「コボットStudio」、ロボットを管理するための「コボットCenter」、実際にロボットを運用・実行するための「コボットAgent」とある。
それぞれの機能が専門性を帯びながらも、たとえばドラック&ドロップで設定が可能など直感的な操作で利用できるため、中小企業など専門的な人材を置けない会社であっても運用は容易だし、運用前や運用後のサポート体制も新たに見直し充実させたサービスということです。
何よりも以前のような「導入したら管理コストで真っ赤っか」みたいな価格ではなくなったので、わたしがコンサルに入っているお客様にも”試しに使ってみましょう”とか気軽にお勧めできるのがいいですね。
詳しくサービスを知りたい方はバナーを張っておくので見に行ってみてください。
わたしの仕事柄ですが、WEBサイトのレポート(広告実績やログ解析のデータを集めて切った張ったしてます…)を作ったり、提案資料の基データを集めたり(提案内容は人がする仕事と自負してますがデータ集めはミスがないほうがいいのでロボットのほうがいいのかも…)って大切ですけど地味に大変だったりするわけで自動化できるところは自動化したほうが良いかなと個人的には思います。
皆さんの業務の中にも、そんな感じの業務がありませんか?
コロナ過で在宅勤務中、会社ではロボットが黙々とデータやレポート作って送ってくれると仕事がはかどるんじゃないかなっと思いますよ。
それでは今回はこの辺で、KOMUSO-WORKSでした。