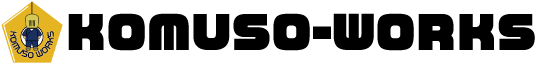意外と簡単に作れる自分オリジナルのスイッチボックス
上の写真、実は私が初めて自作したスイッチボックスです。
実用性を高めるため機能性を考えて配置を試行錯誤したり、それだけじゃなくて見た目にも拘ってみたりホントのレーシングカーのようにとか、スイッチボックスがいくつかコクピットにあるだけで気分が盛り上がりませんか?
そんなわけで今回は、実用性もあり気分も高めてくれるスイッチボックスを自分で作ってみませんか?というお話です。
ステップ1 スイッチボックスで何がしたいかを考える
作る前の段階としてスイッチボックスで何をしたいかを考えます。
これはスイッチの数や種類・配置に大きく関わるためいちばん大事なことだと思います。
ちなみに私の場合はこんな風に考えました。(※当時はVRではなくウルトラワイドでプレーしていました)
・利用はiRacingがメインなのでiRacingでボタン割り当てができる機能
・エンジンスターターやイグニッションスイッチは必ず付けたい!(見た目重視)
・頻度よく使わなくてもあると便利な調整が簡単に行いたい
→ GT3クラス車両でのIN CAR Adjust の設定とか
→ 3~4時間のエンデュランスを走るときの燃料料調整とか
→ ドライバービューの調整(座る高さ)とか
やりたいことは出来るだけ細かくイメージしたほうがいいと思います。
例えば燃料調整はスイッチをひねって調節できるようにしたい…とか、ボタンを2つ使い片方が増量・片方が減量みたいに調整したいとかです。これらは事項の使うスイッチ類に関わってきます。
ステップ2 使うスイッチを選ぼう
スイッチボックスでやりたいことが決まったら次は使うスイッチ選びです。
このスイッチかっこいいとか、琴線に触れてビリビリするとか感性で決めちゃっていいのですが、後述するプログラムで制御するに当たり難易度が跳ね上がったりするので少し説明します。
モーメンタリースイッチ
押している間だけONになるスイッチ。押すとON、離すとOFF。キーボードのボタンとかコントローラーのボタンがモーメンタリースイッチです。実車のセルスイッチみたいにスターターボタンを押したりキーを回しているときだけ作動するイメージでだいじょうぶです。
1回押して離してで1回だけ信号を送るのでスイッチボックスの押しボタン式スイッチはこのモーメンタリー式で基本は問題ありません。
ちなみに写真はAmazonで販売している実車用のスタータースイッチです。
他にもモーメンタリースイッチは色々あるので気になる方は下記のリンクから確認してみてください。
オルタネイトスイッチ
一回押すと離してもONの状態が続くスイッチ。もう一度押すとOFFになります。身近なものでいうと懐中電灯のスイッチやTVやモニターのスイッチとして使われています。
左の画像はオルタネイト式の中でもトルグスイッチと呼ばれるものでレーシングカーにおいてはイグニッションスイッチとして利用されているケースが多いものです。
PCのスイッチボックスで押しっぱなしにしないと行けない機能が余り思いつかないのでオルタネイト式を使用する機会はないと思いますが敢えて挙げるのであれば、上記のイグニッションとかOTSのような押し続ける必要があるけど少し面倒なボタンでしょうか…
他にもオルタネイト式の押ボタンスイッチやトグルスイッチも色々あるので調べてみてください。
ロータリースイッチ
ロータリースイッチとは回転することでON-OFFしたり回路を切り替えたりするスイッチで、身近なものであれば音楽機器のボリューム調整やマウスのセンターホイールなどに使われています。
またアナログ的に無段階調整のものやマウスのホイールみたいにカチカチカチと段階に分けた調整ができるもの、際限なく左右どちらにも回り続けるモノ(マウスのホイール)のあれば上限が決まっていて一定以上回らないモノ(音量のボリューム調整)もあります。
以上のようにとても便利なスイッチですが種類も多く一番混乱しやすいというか買ってみたら使えない(自分がやりたいことができない)という結果になりがちです。ということで私が使っているものをオススメしておきます。
Bourns Inc. 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18
この商品は左右どちらにも際限なく回るタイプのロータリースイッチで1周で18ノック…スイッチのON-OFFがされます。
実際の実例を挙げると、In-Car-Adjustのブレーキバランスやトラクションコントロールの設定を1周あたり18段階上げ下げができます。
またクリックボタン機能もついているので、ツマミでの調整のほかつまみを押すことでもう一つボタン機能をもたせることも可能です。
ある意味、これ一種類で全てのボタンを賄ってもいいんじゃないかと思うほど優秀ですが、このボタンが増えれば増えるほど制御が大変になるので気をつけてください。
注意点としてはロータリースイッチには棒の部分しか付属しておらずツマミ部分は別途用意する必用があります。上記のものには軸径6mmのものがハマりますが一つオススメを追加しておきます。
ポテンショメータ用 ノブキャップ アルミ製 約20mm×15mm 軸穴径 6mm
レースカーっぽく黒で統一したかったのとプラスティックだとやすさが出てしまったためアルミ製のこちらを使っています。
レーシンググローブを着用した状態で操作をすることを考えてつまみ系は20mm小さくもなく大きくもないちょうどいい大きさかと思います。
ステップ3 スイッチボックス本体を決めよう
ここはスイッチを先に決めるべきか、スイッチボックスを先に決めるべきかで迷いましたが好きな(自分がかっこよく思える)ボタンを配置できるボックスにしたほうがいいかなと思い3番目に。
そして私がおすすめするスイッチボックスがこちら。
タカチ電機工業 TS型傾斜アルミケース シリーズ

こちらタカチ電機工業さんのTS型傾斜アルミケースというシリーズで私が利用しているのはTS-2という横長のタイプ。
箱が斜めに傾いているためコクピットに付ける場所と向きをちゃんと考えてあげると座っている運転手側に向かってスイッチを配置できるという戦闘機のようなレイアウトを実現できます。それだけで私のモチベーションは爆上がりでした。
サイズも5種類からあり私の利用しているTS-2で縦横が150mm*200mm。最大のTS-3で210mm*290mmでA4サイズ並みの大きさなのでかなり余裕を持ってスイッチを配置できそうですね。
アルミのままでも十分格好いいのですがもっと雰囲気が出るように渡しの場合はカーボンシートを全面に貼りました。
レーシングカー=カーボンのイメージが勝手にあったので個人的には大満足です。
カーボンシートはサイズ等も色々あるので見比べてみてください。
ステップ4 配置を決める
スイッチボックス本体も決まり、スイッチも決まったのでスイッチボックスの表面サイズを基にスイッチの配置を考えてみましょう。
自分が使いやすいように。
自分から見てかっこよく見えるように。
ここはハッキリ言って好みの問題なので、自己満でいいので簡単な図面(さっきのTS-3ならA4用紙、TS-2ならA4の半分ぐらいなので)ノートやコピー用紙、エクセルなどで作ってもいいので作っておきましょう。
ステップ5 電気工作とプログラムの時間です
ここからは電気工作と作ったスイッチボックスを制御するマイクロコンピュータ(arduino leonardo)のプログラムの話になります…
と思ったのですが、少し長いお話にもなるので次回に分けて話そうかと思います。
それでは今回はここまで。
KOMUSO WORKSでした。